2025.3.18 8:47
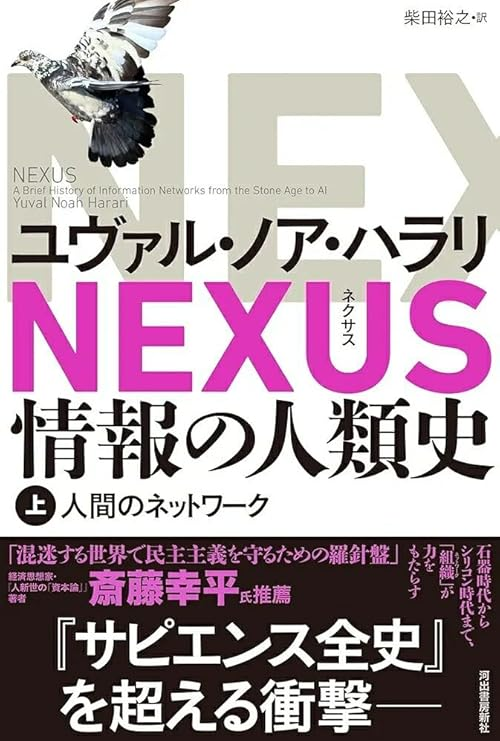
※画像をクリックすると拡大します。
「デジタル時代における教育と科学の役割」
The Role of Education and Science in the Digital Age.
ハラリの新刊「NEXUS」に寄せて、ハラリと講師の対談が東大で開かれ、聴講した(250317-mon)。
ここでのデジタル時代とはつまりAI革命の時代のこと。
おなじみの「物語り(虚構/仮構)」が大切という話から始まる。多くの人を結びつけるには物語りが必要であり、その「物語りの語り手」として、AIが躍り出た。
ハラリの現在のAI観を一言で言えば、AIによってすべてが予測不可能になった、ということのようだ、また歴史上始めてそうなったのだという。
その感覚は自分も確信的に共有しているもの(ハラリに影響されたもの?)だが、今回ハラリはそれを否定してくれるのかも、と少しだけ期待して参加したが、そうではなかった。
「世界がどうなるのかわからない、という事態に、歴史上はじめてなった」
「歴史上始めて」という読み解きはおもしろい。
もちろんいつの時代も未来がわかっていた時代なんてものはなかったのだけど、未来予測の深さと精度は着実に進展していることは確かだった。そういう手応えだけはあった。
しかし、AIがDL〜LLMと進んで来て、未来が一気に予測不可能になってきた。そういうことは歴史上なかった。
大げさだと思う人もいるかもしれないが、そんなことはないと自分は思う。
自己修正メカニズム
登壇者のメディア研究者が、メディアには自己修正メカニズムがあるので信頼できるのだが、AIにはそれはあるか? と問うた。これもおもしろい視点だ。
AIにも自己修正メカニズムはもちろんあるのだが、その「修正の方向」が、やはりよくわからない。
教育について登壇者:「教育に疲れている現象/大学はAIに苦戦している」
AI/コンピュータは何でも答えを教えてくれる。多くの場面で人よりも大局的/横断的な解答を示せる。教育者はどうすればいいのか? 何を教えられるのか?
重要なのは、答えを得て終わるのではなく、問い続ける能力/考え続けられる能力ではないか。
個人的には白眉の話題。
ハラリ:言語・Language(知性であり「数学」も含むものとして「言語」あるいは「Text」)の主人(マスター)は人であったが、その座は完全にAIに取って代わられる。AIとは Language/Text そのものであり、そのTextが、われわれ人に「言い返して」くるようになった。
ここにおいて人はどうすればいいのか?
言語を操っているのは、人の「意識」である。言語で敵わないのならば、われわれは「意識より以上のもの」に賭けるしかないのではないか。
人は、「意識より以上のもの」に賭けるしかない
「意識/言語より以上のもの」とは何かは明確に示されなかったが、例として「親密さ」を、かろうじて上げていた。
親密さとは、自分を気遣ってくれる相手に抱くものである。が、実際には気遣ってくれるだけでなく、相手にも感情(フィーリング)があることが重要で、それを人同士は持てる。
そういう指摘をした後すぐに、AIは感情を持つのだろうか? と自問し、結局それもハラリにはわからない、という。
果たして人はAI(ロボット)を愛するようになるのだろうか?
答えは、イエスとしか思えない。
鉄腕アトムやベイマックスの話が出ていたが、自分が思い出したのは「火の鳥」未来編であり、映画「Her」である。
手塚治虫はアトムを描いた時点でこのことに思いを馳せていたのだろうな、イエスの方向で。
しかし、わたし自身の心に問うと、自分はAI(ロボット)を愛さない/愛せない気がしている。誤解を恐れずに言うと、自分が愛しているのは自分だけだから。自分を愛するために「人を」愛することはできるが、自分のために「ロボット」は愛せない気がする。
とはいえ、やはり本当にどうなるのかはわからないのだが。
最後の話題:
AI革命が投げる哲学的な問い
1. 人と人でない知性を持つものとの関係とはどういうものか?
2. 意識とは何か?
余談だが、開演前の安田講堂の前には10人くらい学生がラウドスピーカーでアジっていた。久しぶりにこういうのを生で聴いた。
「ハラリは、リベラル・シオニストであり、その講演の中止を要求する!」
仮にハラリがシオニストだとしても、彼の話は内容として聞く価値はあると思うのだが、どうなんだろう。

