2024.12.8 15:30
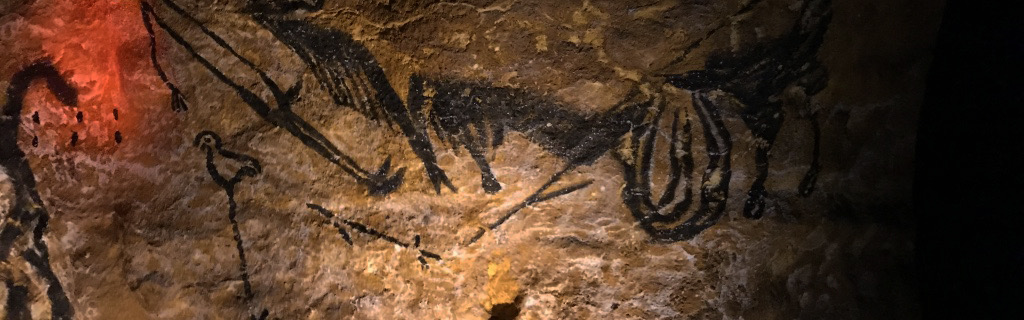
※画像をクリックすると拡大します。
はじめに
デザイン(design)という言葉には「設計」という意味があり、コンピュータも含めていろいろな機械を「設計」することも「デザイン」という。しかしここで話題にしたい「デザイン」は、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、ファッションデザインなどというときの「デザイン」を指しており、「設計」という意味合いはゼロとはいわないが薄い。ややこしい話だが。
私は、このうちの コンピュータ関連のデザイン にかかわっている。現在、この分野はデザイン界の中でもそれなりに大きく重要な位置を占めていると思う。コンピュータのソフトウェアを作るのは基本的にはプログラマーの仕事だが、我々デザイナーも大きな役割を担っている。
コンピュータとデザインには、2つの関係がありうる。
1. コンピュータでデザインする コンピュータをデザインの道具として使うこと。
2. コンピュータをデザインする コンピュータをデザインの対象とすること。
コンピュータをデザインの道具として使うことは、1970年代にCAD/CAMやCGなどから始まり、プロダクトの設計や製造にいたる工程上のアプローチ、プロダクトの外観デザインに関するレンダリング技術として使われていった。その後1980年代にデスクトップパブリッシングがはじまり、印刷出版分野は完全にコンピュータでのデザインや制作に移行した。現在すべてのデザインにとって道具としてのコンピュータは欠かせないし、コンピュータはデザインという仕事を一変してしまった。
しかしここでの話題は、後者の「コンピュータをデザインする」ことにある。「コンピュータ」はそれだけでは何者でもない。「モーターのデザイン」と言っているのと同じことだ。モーターは電気エネルギーから力への変換してくれる機構部品であるように、コンピュータは電気エネルギーを与えると「計算」という仕事をしてくれる機構部品である。コンピュータもモーターも広い意味での「ソフト」が載って、はじめてなんらかの自立した道具になる。ぎゃくにいえば、ソフト次第でそれらは多種多様な機能/目的を持った道具になれるということである。コンピュータは、既存の仕事や道具(機能性)を改善/改良/変革するものでもありうるし、まだ誰も見たこともないような、まったく新しい機能/道具/用途を持った「何か」であるかもしれない。
デザインという仕事は、一般的には製品や印刷物やファッションなどの、おもに美感にかかわることを担当していると思われているのではないか。たしかにそういうことも含まれているが、そうでない部分にもデザインの仕事は及んでいる。コンピュータ・ソフトウェアの例でいえば、画面に表示される美しい情報の「絵」を日々作りだし提案しているが、私たちの「デザイン」はそれだけではない。
「コンピュータデザイン」
このデザイン分野が実質的に生まれたのは約40年前のことであるが、私自身はその歴史の0年からかかわっている。というか、この分野をなんとか立ち上げようとしてきたサイドのデザイナーである。自分で言うのもおこがましいが、いわばこの分野の「生き証人」である、ホント。
「コンピュータデザイン」という言い方は、ありそうであまり聞かない言葉である。その語感には自分でも引っかかりがある。他にもこのデザインの呼び名はあるわけだが、どれもしっくりくるものがない。たとえば、UIデザイン、UXデザイン、情報デザインなどなど。
自分は「コンピュータをデザインする」分野の中に長くていて「コンピュータ」や「デザイン」についての、自分なりの新しい観念というものも抱いている。しかし、思いがあるからこそ、まだこのデザインをうまく「これ」と名指すことができないでいる。なので、ここで中途半端な名前に飛びつかないで、あえて、身も蓋もない「コンピュータデザイン」という名前で呼んでおくことにする。
この活動の「本当の名前」を考えること自体が、ここでの思考の目的であるといえるのかもしれない。
ここでは、コンピュータデザインの具体的な例をとりあげながら、より大きな「人」の活動や行為、営みとしての「デザイン」について考えていきたい。
(つづく。 以後、しばらく継続的にこの議論を続けていくので、お楽しみに。)
(241208)

